お稲荷様の正しい参拝方法|願いが叶う人が守っている神社マナーとは?

神社へ参拝するには様々な作法があります。
作法とは神様に対する崇敬の心の現れですので、神様に失礼の無いよう参拝したいものです。
特に怒らせると怖いお稲荷様。
正しい参拝で幸運を引き寄せましょう!
今回は願いを恐ろしいほど叶えてくださる、お稲荷様の正しい参拝方法をご紹介します。
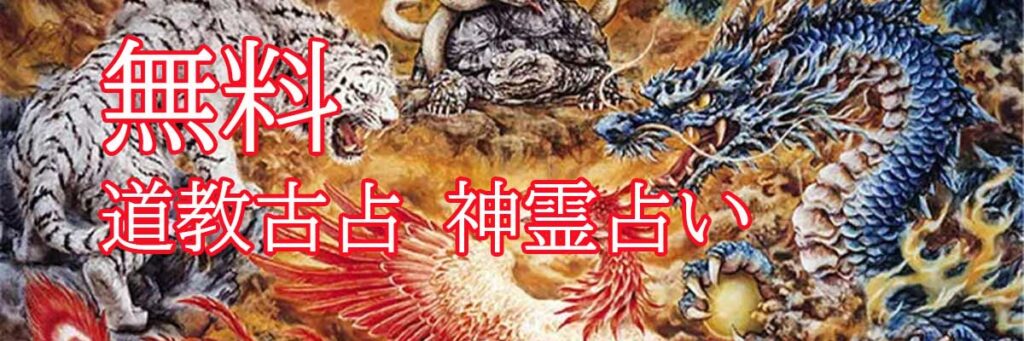
あなたを守護する神霊を生年月日と性別から占います。
詳しくは、霊符付きメール占い|道教古占・太平命理・干支命理の無料占いで「あなたの神霊」を知るをご覧ください。

【無料】カバラ数秘術をプロ鑑定士が個別診断|生年月日をLINEで送るだけ
目次
基本的な一連の流れ
神社のお参りの正しい作法は、「二礼二拍手一礼」
お賽銭箱の前に立つ。(帽子をとり、荷物を置く)軽く会釈をする。
お賽銭をあげる。鈴を鳴らす。
姿勢を正して
(1)深く二回お辞儀をする。両手のひらで自分の膝頭を覆うくらいまで深く(約90度)頭を下げる。
(2)両手を胸の高さで合わせ、右手の中指を左手の中指の第二関節あたりまで下げてから、両手を肩幅あたりまで平行に開き、ゆっくり二回拍手を打つ。二回目の拍手をしたら両手を合わせ祈願を込める。
(3)最後に深く一礼する。軽く会釈をして下がる。
詳しくは次より解説いたします。
お稲荷様への参拝の作法

神社へ参拝するには様々な作法があります。
作法とは神様に対する崇敬の心の現れですので、神様に失礼の無いよう参拝したいものです。
境内は神様がお鎮まり成る神聖な場所です。
境内に出入りをするときは鳥居の前で神前に向かい一礼をします。
手水で清める
神社では「穢れ」を最も嫌うためまず手水で心身を清めます。
この手水は海や川で行われた「みそぎ」を簡略化したものと考えられています。
手水の作法はまず右手で柄杓をとり、水を汲み左手を清めます。
柄杓を左手に持ち替えて右手を清め、又右手に持ち替えて左手で水を受け口を漱ぎます。
この時柄杓に直接口を付けてはいけません。
水を吐き出す時は低い位置で手で口元を隠すようにします。
最後に柄杓を立て残った水で次の人の為に柄杓の柄を清めて柄杓を元の位置に伏せておきます。
神様に拝礼する前に身を清めてから、清浄な身と心で神前へ進もうとする日本人の習慣なのです。
お稲荷様への拝礼
神社の前まで来たら、鈴を鳴らしてその清浄な音で清め、賽銭は投げずに近くから静かに入れます。
賽銭を投げ入れる方がいますが、それは失礼な行為です。
そして「二拝二拍手一拝」の作法でお参りします。
まず約九〇度腰を折って二度深く頭を下げ、次に二度拍手を打ちます。
静かに心中で祈願をした後、もう一度頭を下げます。
本殿での参拝を済ませた後、各末社や奥社奉拝所、稲荷神社といった境内各所を巡拝するのが正しい参拝なのです。
もしもっと丁寧に神様へ自分の気持ちを伝えたいという人は、本殿での御祈祷をお受けになるのをおすすめします。

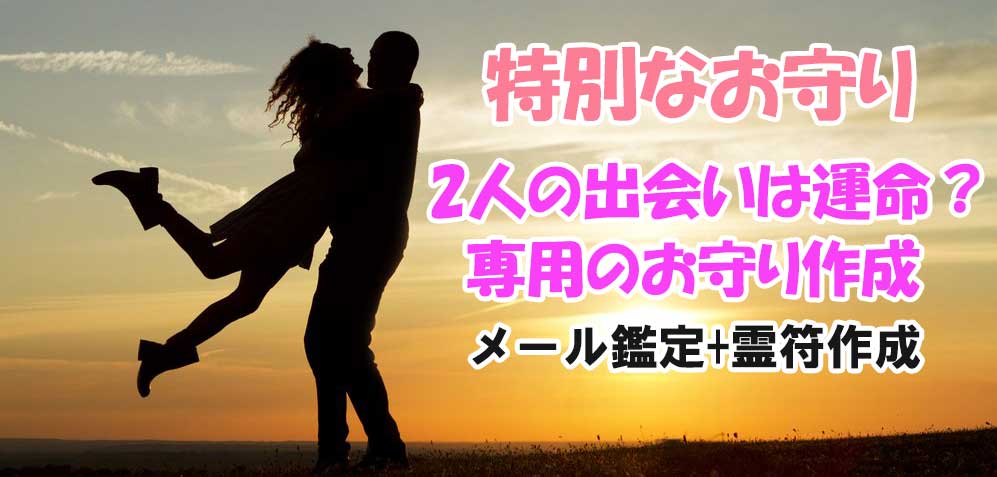
願いを届ける 感謝を届ける
あなたの願いを伝える前に、流れがあります。
1.住所、氏名、生年月日、干支、年齢を伝える
2.日々の生活の感謝を伝える
3.世界平和や地域の平和を願う
4.あなたの願いを伝える
どこの誰かも伝えずに願いを伝えられても神様だって困ってしまいますよね。
九尾の狐の置物を扱っております。カワイイので是非、ご覧ください。

稲荷神社とは?

ここまで読んでくださった方は、稲荷神社とは何?という方も少ないと思いますが、お稲荷様への正しい知識を持って参拝する為に、復習も兼ねてお読みください。
神道では宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)が、正式な呼び名となります。私たちは親しみを込めて稲荷神社の神様のことを「おいなりさん」「お稲荷様」などと呼ぶことがおおいのではないでしょうか。
稲荷神社は全国に32000社もあります。これは2番目に多い八幡神社は25000なので圧倒的に多い数。
そして日本の神社の中で最大の勢力を持つのが稲荷神社です。総本社は京都の伏見稲荷。
稲荷神社の成り立ちは諸説あるのですが、伏見稲荷神社で紹介されている説を紹介します。
昔、伊呂具(いろぐ)という裕福な豪族の棟梁がおりました。
伊呂具がある日、お餅を的にして矢を射ってました。すると、おもちが白い鳥になって飛んでいってしまいました。
その白い鳥が降り立った峰は稲が多く実り、棟梁は神様がなさったことだと思い、そこに社を建てました。そこから「稲生り」⇒「稲荷」となりました。
稲荷神社のキツネは神様?

稲荷神社の象徴でもあるキツネさんはどのような存在なのでしょうか?
キツネは、神様の眷属(けんぞく)なのです。
眷属(けんぞく)とは、神様の使者という意味です。
つまりキツネはお稲荷さんの使いということになります。
大昔、私たちのご先祖様方は、キツネを神聖な動物として捉えていました。
それは、キツネが農事が始まる春先から秋の収穫期にかけて里に降りて姿を現し、収穫が終わる頃に山へ戻っていくため、農耕を見守る守り神のように考えられていたからという説があります。
人々は、そんなキツネを目には見えない霊獣「白狐(びゃっこ)」として信仰し、五穀豊穣の神様「お稲荷さん」のお使いだと考えました。これが稲荷神社にキツネが鎮座するようになった由縁です。
※他にもさまざまな説があります。
稲荷神社のご利益は?

お稲荷様は、願いを叶えてくれる力が特に優れていると言われます。
しかし、その反面、願いを成就した時のお礼は必ず必要とも言われます。
願いを叶えた報酬を忘れてしまうと、逆に悪い結果に繋がってしまう場合も、よく耳にします。仏教でも狐を眷属に持つダキニテン様も同様に、強い力を持っていますが、やはり失礼な事をしてしまうと、とても怖い仏様です。
「五穀豊穣」がもともとのご利益でしたが、平安時代には「良縁」や「病気平癒」のご利益も授かれるようになり、今では商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達など幅広くご利益があります。
商売繁昌 家内安全 交通安全 厄除 開運招福 入試合格 学業成就 大漁満足 海上安全 良縁 心願成就 初宮 旅行安全 安産 子授 病気平癒 七五三詣

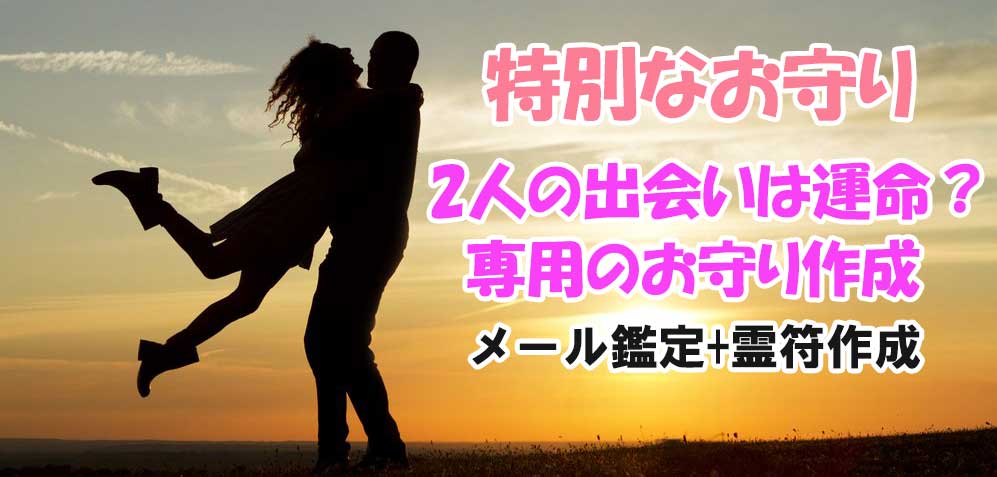
お稲荷さまの初午祭とは?
二月最初の午の日
毎年、二月最初の午(うま)の日には、全国各地の稲荷神社で「初午祭」が斎行されます。
これは、伏見稲荷大社の御祭神が降臨された日が2月11日(または9日)で、この日が初午の日だったという言い伝えによるものです。
また、春に山の神が降りてきて田の神になり、秋にはまた山へ帰って行かれるという民間信仰とも関連しており、2月の初午に「山の神を迎える」という意味を込めて、祭りが定着していったとも考えられています。
伏見稲荷大社では、この日朝8時から「初午大祭」が行われ、初午詣に多くの参拝者が訪れるようです。初午の日にちは、毎年変わります。
稲荷神社は参拝を辞めると祟られるってホント?

結論からいいますと、参拝を辞めたから祟られる事はありません。
そんな理不尽な神様じゃないので、ご安心ください。
たしかに、稲荷神社には実に多くの怖い噂が流れています。
ほとんどが迷信なのですが、こういうことを聞くといくら信じてないといってもなんとなく参拝を敬遠してしまうもの。
とっても残念なことです。
なので1つ1つ誤解を解いておこうと思います。
一生参拝しなければ祟られる?
お稲荷様に限らず、可能なら何度でも参拝した方が良いに決まってます。
でも絶対参拝しなきゃいけないってことはありえません。
ましてや祟られることもありません。
そんなこといったら稲荷神社に参拝した観光客はみんな祟られてしまいます。
お願いを代償が必要?
神様が「交換条件が必要だ」なんて取引きはしません。
ただし、あまりにも身勝手なお願いは、代償どころか、それ以上の事が起こってしまうかもしれません。
お礼参りはしないとダメ?
お願いが叶ったらお礼に行くのは当然です。
これは人間社会にでも基本的なことなのですが、人に何かしてもらったら感謝したりお礼の品を贈ったりします。
稲荷神社に限らず、願い事が叶った際は神社にお礼参りした方がよいです。
普通の神様ならば寛容ですので、心の中でお礼をする程度でも事情があれば仕方ないかもしれません。しかし、お稲荷様にお願いしたのであれば、必ずお礼は必要です。
叶う力が強いという事は、反面の力にも大きく作用する事を忘れないでください。
まとめ
今回は、稲荷神社について紹介しました。
お稲荷さんとは、宇迦之御魂大神という稲作・農業の神様で、キツネはその眷属(神の使い)だったんですね。
厳密には、キツネ自体を神とする信仰もありますが、本来は「お稲荷さんの眷属」だということを覚えておくと良いかもしれません。
神社好きの方でも半分の人は知らなかったこのキツネさんの立ち位置。
神通力の高い稲荷神社で願いを叶えましょう!
九尾の狐の置物を扱っております。カワイイので是非、ご覧ください。

荼枳尼天に関しての、もっと詳しい記事はコチラから。
【総集編】荼枳尼天の信仰と解説|稲荷信仰と習合した神秘の女神とは
荼枳尼天のカテゴリ一覧から記事を探す
コメント
この記事へのトラックバックはありません。










この記事へのコメントはありません。